164-1 保月(ほつき)六面石幢・宝塔
岡山市の北西約30kmの山間に高梁(たかはし)市があります。日本一高い山城備中松山城を誇っています。JR伯備線高梁駅から北東約16Kmの上有漢(うかん)の山里にすばらしい六面石幢です。一面に七仏+五面五仏=十二仏像が刻まれています。「十三仏成立過程を示す遺物として注目される」と日本石造美術辞典241pに記載があります。(以下、美術辞典と略称)
 |
| 道路から見上げた所、正面が六面石幢、右が宝塔です |
 |
| 嘉元四年(1305)、もとの請花宝珠の代わりに小五輪塔部分が載せられています |
 |
| わが国最古の石幢がこれほどの状態で保存されていtビックリ |
下の宝塔は基礎の刻銘に「奉刻彫・・五輪塔婆一基・・」とあるので元は五輪塔ですね。こちらは嘉元三年(1305)で大工伊野行恒は同じ作者。


164-2 保月三尊板碑
六面石幢への道路沿い斜面に斜めに傾いで建っています。高さ3.1m花崗岩で重厚感があります。上から釈迦・定印阿弥陀・錫持地蔵の三尊を刻みます。これらの3基とも「大工伊野行恒」の銘をもち大和の伊派の一人の手になるものです。同じ板碑でも関東の青石板碑との違いにビックリです。


164-3 土居の二尊板碑
中国自動車道有漢IC西方を通る県道49号線の、土居集落はずれの道路沿い石垣上に小屋根をかけてに祀られています。下の解説板「遣迎二尊」(けんげいにそん)とは此岸にあり往生者を見送る釈迦如来と、彼岸である浄土からこれを迎えに来る阿弥陀如来のことをいうそうですね。勉強・勉強。


昼食は「うかん常山公園」でした。風速3m(すすきが揺れる程度)で回る石の風車が7基18風車があるユニークな公園でした。

164-4 祇園寺の宝塔・十三重石塔
高梁駅北15kmの祇園山高所にある祇園寺。大杉は大山に行く天狗が羽を休めたので天狗杉とか、1200年の樹齢だそうです。
境内隅に石段をくみ上げ建立されています。軸部に四方佛(釈迦・薬師・弥勒・阿弥陀)を彫り、笠には風鐸を吊った穴があります。年代は刻まれていませんが、美術辞典では鎌倉後期に分類されています。
境内の反対隅には、市有形文化財指定の十三重石塔が建っています。
![s-史美会岡山備中高梁見学会2015-03-21祇園寺宝塔十三重石塔024k] s-史美会岡山備中高梁見学会2015-03-21祇園寺宝塔十三重石塔024k]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLEdsaooyXAT7JnYD66wC_mxNlgCuplUseLPboY3B0kHjdIMEH6FsSMGvi0otCYk6umxEXxT15iow4jAYat5o7iK9P1iMwU5p2aol-Jp7RDPBKtAB5Zg_HWb7lt882um_ePbKykZuNGolS/?imgmax=800)
竜泉寺からの帰路、参道に六角が建っていて素通しの壁際に8基程大師塔・地蔵塔などが祀られています。その参道際に4基の石塔が並んでいます。左から納経百八十八箇所供養塔・南無阿弥陀仏名号塔・享保の錫持地蔵・文政の常夜灯です。自然石を利用した独特のものです。往時はにぎやかだった所から集められたのでしょうか、ちょっとバラバラ。
 |
| 右に見える東屋風の建物が六角堂、石仏が見えています |
瀬戸内第十四番観音霊場竜泉寺は高梁駅から西方8kmのところにある、真言宗善通寺派(この地区は多いですね)のお寺で本堂前の白砂がきれいなお寺です。
境内の片隅に屋根をさしかけて角柱状に建てられています。
 |
| 元享四年(1324)来迎阿弥陀像が柱状に刻像 |
帰り道、庚申堂の表示があるお堂をのぞくと奥におられたのが下の写真の神様です。石造ではないですが、多分六肘の青面金剛様ではないでしょうか?

164-6 恵堂(えどう)の地蔵石仏
備中高梁駅から西へ約4km、成羽川沿い国道313号線地蔵前バス停におられます。石灰岩で高さ1.85mの延命地蔵です。岡山県で2番目に古いとか。


164-7 頼久寺庭園(小堀遠州作?庭園)
小堀作助政一(遠州)が備中松山城を継いだ時、城が荒れていたためこの寺で政務を執ったとか。その頃に作られた蓬莱式枯山水式庭園で、鶴島・亀島・サツキの青海波・愛宕山借景など桃山江戸初期に好まれた傑作庭園とか。
とはいえ、S会員から遠州作庭などを含めた現状理解に関する詳しい説明をいただきました。
 |
| 正面が愛宕山、三段に見えるサツキが青海波、その手前が鶴島です |
 |
| 火袋の穴の丈夫に仏(地蔵?)のお顔が見えます |
 興味深いのは庭園隅の石灯籠です。暦応二年(1339)西念勧進の石灯籠ですが火袋が四面とも浮き彫りの仏身を刳り抜いて作られています。会員同士が見つけて大いに盛り上がりました。なんでだろう。
興味深いのは庭園隅の石灯籠です。暦応二年(1339)西念勧進の石灯籠ですが火袋が四面とも浮き彫りの仏身を刳り抜いて作られています。会員同士が見つけて大いに盛り上がりました。なんでだろう。 164-8 備中松山城と城下町
高梁は岡山の小京都といわれるような町並みです。

 備中松山城は「天空の城」にもなぞらえる山城です。兵庫但馬の竹田城は標高353mですが、こちらは天守閣つきで430mの高さにあります。雲海に浮かぶ天守閣は地元の人のご自慢です。駅前の通りから見ると標高差は360mですね。
備中松山城は「天空の城」にもなぞらえる山城です。兵庫但馬の竹田城は標高353mですが、こちらは天守閣つきで430mの高さにあります。雲海に浮かぶ天守閣は地元の人のご自慢です。駅前の通りから見ると標高差は360mですね。
 |
| 正面山頂が切れ込み状ですがこちらに天守閣が |

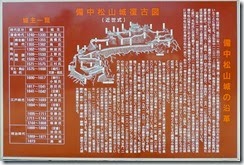
164-9 清水寺(せいすいじ)平清盛供養塔
JR高梁駅の北西12km、隣町吉備中央町の山里に天台宗清水寺があります。清盛が仁安三年(1186)に十二坊を建立、寺領三百石を寄進したとの由緒。

 花崗岩製総高2.6m、塔身正面に胎蔵界大日如来を刻み銘文はない。鎌倉後期から南北朝の作との推定。寺の由緒書で清盛の供養塔と伝え「西国で海路から遠く離れた史跡は珍しい」と吉備中央町史に書かれているようです。
花崗岩製総高2.6m、塔身正面に胎蔵界大日如来を刻み銘文はない。鎌倉後期から南北朝の作との推定。寺の由緒書で清盛の供養塔と伝え「西国で海路から遠く離れた史跡は珍しい」と吉備中央町史に書かれているようです。 宝塔のある高台の下には西国33観音霊場の主尊が勢ぞろいされていました。
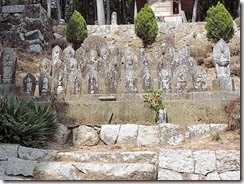
164-10 加茂総社宮 (リンク先のWikiprdiaで由緒をご覧ください)

樹齢160~550年の杉の巨木が自ずから由緒ある荘厳感を漂わせます。こちらには、県指定の康安四年(1281)の安山岩製八角灯篭と貞治四年(1365)和泉砂岩製地蔵塔が見学対象です。


 |
| 本殿脇柵ないに灯篭と地蔵 |
岡山県足守駅北9kmにある備中国二宮と伝える神社。境内はずれに、今回見学で一番の見応えある宝塔です。総高4.18m、塔身正面は深い龕に金剛界大日を厚彫りし、側面は扉型の模様。笠軒裏も繁垂木を掘り出し圧倒的な存在感ある宝塔でした。貞和二年(1346)沙門正因が勧進元をつとめ大工妙阿が造塔しています。「沙門」とは僧侶であると辞書にありますが、当時は修験道と密接に結びつきがあったと推測したいですね。関東の大日塚・大日塔を連想してしまいます。

 廃神林寺の遺物のようですが、これだけのものが山中の神社に残されている事に驚きますが、岡山の石造文化の懐の深さに感心しました。神社の山門に随身がおられました。由緒あるんだ。
廃神林寺の遺物のようですが、これだけのものが山中の神社に残されている事に驚きますが、岡山の石造文化の懐の深さに感心しました。神社の山門に随身がおられました。由緒あるんだ。 

164-12 足(葦)守八幡神社石鳥居
岡山空港の南西5km、国道429号線近くに葦守神社が鎮座します。その南参道入り口に中国地方最古の石鳥居があります。「笠木の反りや先端を垂直に切ったところは鎌倉時代の形式である」(美術辞典)そうです。


二日間にわたり中国地方の有名な石造物や庭園を見学することができました。さらに会員の皆さんでいろいろな指摘や解説をいただいた事は貴重な経験でした。ありがとうございました。

0 件のコメント:
コメントを投稿